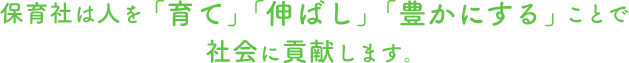会社情報
ビジョン
保育社は、2007年5月より、「育てる」「伸ばす」「豊かにする」のコンセプトで
新しい展開への一歩を踏み出しました。
そして、『伝統』をベースに『革新』をトッピングし、新しい‘保育社ブランド’を作り上げていきます。
新しい保育社にご期待ください!
- 保育社のフェイスマーク
- 「育」の一部分をとった保育社のフェイスマーク。
目にした人が思わずほほえんでしまうような、保育社の商品作りへの願いを込めています。
会社概要
| 社 名 | 株式会社保育社 |
|---|---|
| 設 立 | 2007年(平成19年)4月6日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷川 翔 |
| 本社所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階
電話:06-6398-5151 FAX:06-6398-5157 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 江坂支店 |
| 事業内容 | 1)書籍(実用書、文庫、新書、文学・歴史・美術など)、雑誌、辞典、図鑑、児童書、コミックなどの企画・出版 2)DVD、CD-ROM、VTR、電子書籍などの企画・制作 3)研修会、セミナー、イベントの企画・運営 4)異業種交流等コミュニティ、スペースの企画・運営 5)上記各号に付帯関連する一切の事業 |
| 主な出版物 | 児童書・教育書を中心に刊行 すごいぞぼくらのからだ!シリーズ、医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ、?(ギモン)を!(かいけつ)くすりの教室シリーズ、生きもの摩訶ふしぎ図鑑シリーズ、絵本や自然科学・英語教育書関連書籍 など |
| 受賞歴 | 平成27年度埼玉県推奨図書/『すごいぞ!ぼくらのからだ』シリーズ「こころとしんぞう」選定。 第17回学校図書館出版賞/『医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ』受賞。 第28回「よい絵本」(全国学校図書館協議会)/『すごいぞ!ぼくらのからだ』シリーズ「ほね・ホネ・がいこつ!」選定。 |
| 主な取引先 | 株式会社トーハン、日本出版販売株式会社、楽天ブックスネットワーク株式会社 、株式会社中央社、株式会社日教販、株式会社西村書店、株式会社鍬谷書店、大村紙業株式会社 |
| 主な加盟団体 | 日本児童図書出版協会、教育図書出版会 |
保育社は 株式会社メディカ出版の100%出資会社です。
沿 革
| 1946年(昭和21年) | 大阪市南区にて創業、翌年東区に移転。 おもに幼児用絵本、童話、小学校の社会・理科の副教材を発行。 小学校、中学校の参考書、学習辞典、学習図鑑。 |
|---|---|
| 1962年(昭和37年) | 「カラーブックス」刊行。これを機に『見る文庫』で広い読者層を対象に。 |
| 1972年(昭和47年) | 昭和天皇の観察記録「那須の植物誌」を刊行 |
| 1976年(昭和51年) | 「萬葉大和路」にて『世界でいちばん美しい本』ゴールドメダル受賞 |
| 1977年~1980年ごろ | 「仏像大和路」「吉兆」「日本の民家」「大和路有情」など刊行 「日本の民家」では日本写真製版工業組合会長賞を受賞 |
| 1986年(昭和61年) | 保育社創立40周年記念誌刊行 |
| 1999年(平成11年) | 和議を申請。 その後出版社や文化人、書店などが経営再建の支援により、 既存の原色図鑑シリーズ、検索入門シリーズなどを主体に増刷出版が続けられる。 |
| 2007年(平成19年) | 5月より株式会社メディカ出版の出資により、新生「保育社」としてスタート |
| 2012年(平成24年) | 児童書分野に参入 |
| 2013年(平成25年) | 07月: 絵本プロジェクト制作『すごいぞ!ぼくらのからだ』シリ-ズ創刊。 「たべものたべたら」「ぼくの手 わたしの手」「ほね・ホネ・がいこつ!」「あしってエライ!」「こころとしんぞう」全5巻 |
| 2014年(平成26年) | 12月:「医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ」刊行開始 |
| 2016年(平成28年) | メディカ出版グループ 保育社10周年(創業70周年) |
| 2017年(平成29年) | 08月: クラウドファンディングを活用して子どものための英語教材『ホイッキーとおうち☆えいごじゅく』(音声ペン付)を制作・刊行。 |
| 2018年(平成30年) | 01月: ?(ギモン)を!(かいけつ)くすりの教室シリーズ刊行開始 |
保育社を応援する人々
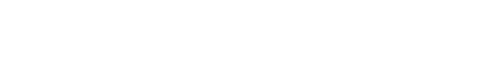

やくみつる(1959年3月12日生)
漫画家。スポーツ評論家。早稲田大学商学部卒業。漫画家だけでなく、テレビのコメンテーターなどのタレント活動もしている、保育社が1999年に和議申請した際には、連載中の週刊誌で「保育社ナシでは生きてゆけない!!」という漫画を執筆して応援。日本昆虫協会所属。
カラーブックスの金魚がはじめての出会い
いちばん初めに保育社の本を買ったのはカラーブックスの「金魚」(初版昭和38年)です。まだ幼少のみぎり(笑)、金魚に興味をもって本屋さんに行って、自分で選びました。その次に買ったのが「世界のミニカー」(初版昭和42年)です。小学校の3、4年ですかね。当時、文庫本サイズのお手ごろな値段で、「しかもカラーで印刷しているのがある」と嬉々として買いましたよ。
その後、学生になるにつれて、「標準原色図鑑」(絶版)そして「原色図鑑」へと発展していくわけです。私は身の回りにいる生き物などの名前がわからないままだと気持ちが悪くてしょうがないんです。いや、気持ちが悪いっていうよりも、「その生き物たちに対して失礼だ」なんて思っちゃうんです。だからたった1種類の名前を調べるために図鑑を1冊買うなんてこともありますよ。そのなかで保育社さんの図鑑が知らず知らずのうちにそろっていったのでしょう。
図鑑から興味が広がることもある
保育社の図鑑の魅力というのは、詳しさもさることながらそのラインナップの広さですね。最初は「昆虫」の図鑑から入るとしますよね。それが「甲虫」や「蝶類」「蛾類」というふうに広がり、さらに「幼虫」の図鑑にまで広がっていく。湧きあがってくる知りたい欲求に対してラインナップがされているところ、こちら側の好奇心を受け止めてくれるところが保育社の図鑑のよさです。
いっぽうで図鑑がきっかけで、自分の興味が広がることもあります。「原色日本蛾類幼虫図鑑」ってありますよね。蛾ですよ。成虫でもナンギなのに「幼虫」(笑)。でもその図鑑を見たときに蛾の幼虫への興味がパーッと広がりました。それまで見かけた蛾の幼虫を同定(生物の分類上の種名を決定すること)しようとまでは思わなかったのですが、この図鑑があればそれができる。そんな図鑑があることによって、自分の興味が広がることもあるのです。
いつか「図鑑の完成形」を突き詰めてほしい
保育社の図鑑は写真だけでなく、多くのイラストが使われていますね。自分が絵を描くことを職業としてから、改めて見ると、この1冊の図鑑を仕上げるにはいったいいくらイラスト料がかかっているんだろう?と思います。イラスト1点1点に掛かる労力を考えるとすごいものがあります。
「図鑑はすべての既知種を網羅していなければならない」としたら、完成形を作ることは非常にむずかしいですね。でも保育社さんにはいつかは完成形を突き詰めていただきたいと思います。